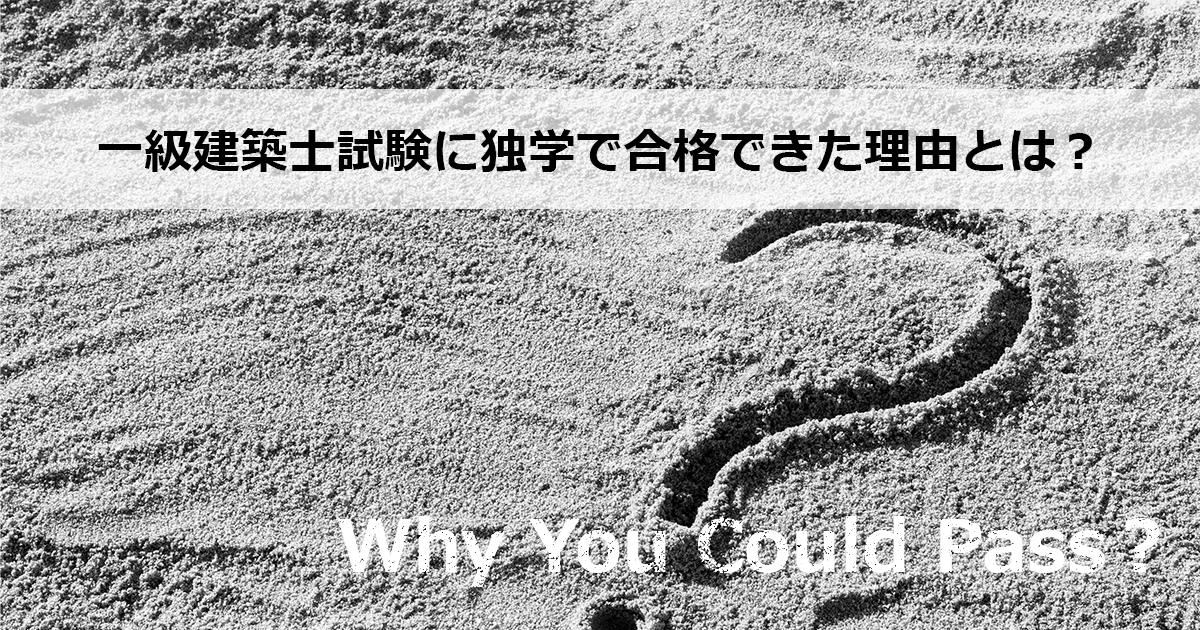こんにちは、独学家(セルフ・ラーナー)のKuroです。
このブログでは、独学での大学受験や一級建築士試験、海外留学についてのノウハウを発信しています。
こちらの記事では、一級建築士試験(学科・製図)に独学で一発合格したKuroが、一級建築士試験を独学で突破できた理由を振り返ってみます。

結論を言うと、一級建築士試験の内容を楽しく学ぶことができたということに尽きるかもしれません。
はじめに
ブログ主のKuroは、平成30年の一級建築士試験に独学で合格しました。
インターネット上では独学での合格は難しいと言われていたり、また知り合いに独学で合格したことを伝えると驚かれることも多いです。
そこで、こちらの記事ではなぜ独学で合格できたのかをKuroなりに振り返ってみたいと思います。
独学で合格できた理由(学科・製図共通)
まず初めに、学科、製図試験に共通した要素を挙げてみます。
勉強が好き
一番大きな理由は、そもそも勉強が好き(趣味)ということが挙げられます。
大学受験の頃は毎日勉強に明け暮れましたし、社会人になっても毎日時間を取って何かしらの勉強を継続するようにしていました。
そのため、一級建築士試験の勉強は全く苦にならず、自主的に勉強時間を確保して毎日のスケジュールに沿いながら勉強を継続しました。
特に学科試験は毎日の勉強時間をしっかり確保して集中して勉強できれば、独学でも十分に合格できます。

逆に言うと、毎日の勉強スケジュール通りに勉強できない人や、集中力が欠けてしまうような人は、資格学校へ通って強制的に勉強した方が良いかもしれません。
学びたい分野と合致
二つ目の大きな理由は、建築を学びたかったということが挙げられます。
Kuroは建築・土木系の学科を卒業しましたが、建築に関する知識はあまり持ち合わせていませんでした。一方で、社会人になると建築の知識を要求されることが多くなったことから、何とか建築を勉強したいと思っていました。
そのような時に一級建築士試験は格好の勉強対象でした。建築の概要を学ぶことができますし、また合格すれば一級建築士を名乗ることができます。

勉強好きが相まって、毎日楽しく一級建築士試験の勉強を行いました。
独学で合格できた理由(学科試験)
次に、独学で学科を合格できた理由を振り返ってみます。
数学(構造)が得意科目
学科を独学で合格できた一つ目の理由は、数学(構造)が得意科目だったことが挙げられます。
構造は数式が含まれることから、得手・不得手が分かれる科目です。Kuroは数学が得意であったため、学科Ⅳ(構造)に出てくる数式は特に問題なく理解することができました。また、基礎的な理解で応用できる範囲が広いため、得点源として考えていました。
試験結果のこちらの表をみても、結果的に学科Ⅱ(環境・設備)と学科Ⅳ(構造)で得点を稼いだ形となっています。
| 学科Ⅰ (計画) | 学科Ⅱ (環境・設備) | 学科Ⅲ (法規) | 学科Ⅳ (構造) | 学科Ⅴ (施工) | 合計点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格点 | 11/20 | 11/20 | 16/30 | 16/30 | 13/25 | 91/125 |
| Kuroの得点 | 14/20 | 18/20 | 23/30 | 26/30 | 18/25 | 99/125 |

学科Ⅳ(構造)は配点も大きいことから、ここを得点源とできるかどうかは独学合格を目指す上で重要です。
試験日前に集中的に勉強
学科を独学で合格できた二つ目の理由は、試験日前に集中的に勉強できたことが考えられます。
受験した当時、Kuroは海外駐在しており、試験へ向けた日本への一時帰国と合わせて長期休暇を取得しました。そのため、試験日前の10日間は毎日図書館に通い、一日10時間ほど集中的に勉強することができました。

学科試験直前の10日間で100時間勉強しました。
学科試験はいかに多くの知識を暗記できるかが勝負です。しかし、一度暗記しても時間が経つと忘れてしまうのが人間です。試験前に集中的に勉強することで、暗記した内容を効果的に試験で生かすことができます。
独学で合格できた理由(設計製図試験)
次に、製図試験に独学で合格できた理由を振り返ってみます。
製図合格に必要な能力を養成
まず初めに、製図試験に合格するために必要と考えられる能力を効果的に養ったことが考えられます。
ブログ主のKuroは、製図合格にはプランニング力、製図力、記述力の3つが必要と考えています。(公財)建築技術教育普及センターが掲載している過去問や、「製図試験のウラ指導(教育的ウラ指導)」、「設計製図試験課題対策集(日建学院)」を効率的に使用して、これらの能力を養ったことが合格に繋がったと考えています。
パズルが得意
次に考えられる理由としては、パズルが得意であることが考えられます。
製図試験は、与えられた要求室を上手く敷地内に配置する(ゾーニングする)試験です。各要求室の関係性や必要面積を検討して、それを3次元的に配置することが求められます。これを上手く仕上げるためには、建築物を立体的に捉える空間把握能力が求められると考えられます。
その中で、ブログ主のKuroは元々パズルや地図を読むのが得意でした。もしかしたら、要求室を立体的に落とし込むことも得意な方だったのかもしれません。

プランニングする時のコツは、アプローチを決めた上で、コア(階段+EV)と大きい要求室(要求面積が大きい+複数回に跨る要求室)の配置を同時に考えることです。要求室の配置方法は無限にありますが、コアと大きい要求室の配置をある程度決められれば、他の要求室を配置する自由度が減ってエスキスを進めやすくなります。
試験問題との相性
最後に考えられるのは、試験問題との相性が良かったことです。
平成30年の課題は廃校となった小学校の跡地において、温水プールのある「健康づくりのためのスポーツ施設」を計画するものでした。計画に当たっては、敷地内のカルチャーセンター、全天候型スポーツ施設、屋外グラウンドとの一体的利用が求められ、どこからアプローチをとるかが重要なポイントでした。
Kuroは、この課題を一読した直後に桜並木のある西側からアプローチをとることを決めました。西側にメインアプローチを置けば、面積が大きく且つ2層に跨って配置しなければいけない屋内プールは自然と東側に配置することになり、また消去法的に多目的スポーツ室は2階の西側に配置することとなりました。
ここまでプランニングができれば、残りの要求室をゾーニングすることは難しくありません。

アプローチが決め手となった平成30年の課題において、直ぐに正解のアプローチを導き出せたことは幸運でした。
まとめ
こちらの記事では、一級建築士試験を学科・製図ともに独学で一発合格できた理由を振り返ってみました。
いろいろと振り返ってみましたが、一番大きな理由は建築を楽しく学ぶことができたということに尽きるかもしれません。新しい知識を得て、それを定着させ、今後の仕事に役立てることができるかと思うと、Kuroは試験勉強することが楽しくて仕方ありませんでした。
最後に、理由をまとめるとこちらとなります。
- 勉強が好き(共通)
- 建築を楽しく学んだ(共通)
- 数学が得意(学科)
- 試験日前に集中的に勉強できた(学科)
- 製図試験に必要な能力を効果的に養った(製図)
- パズルが得意(製図)
- 試験問題との相性が良かった(製図)

最後までご覧いただきありがとうございました!